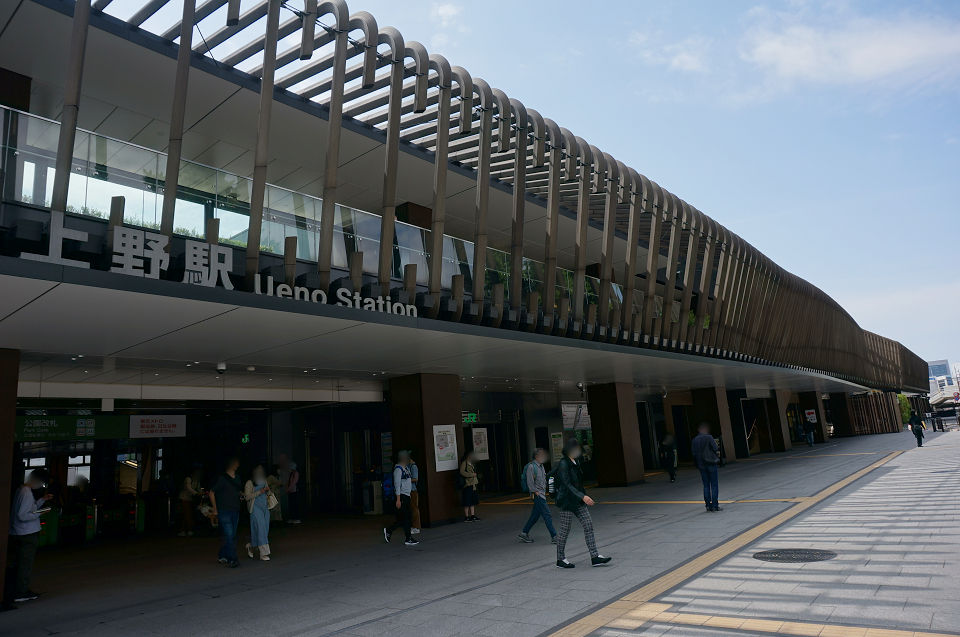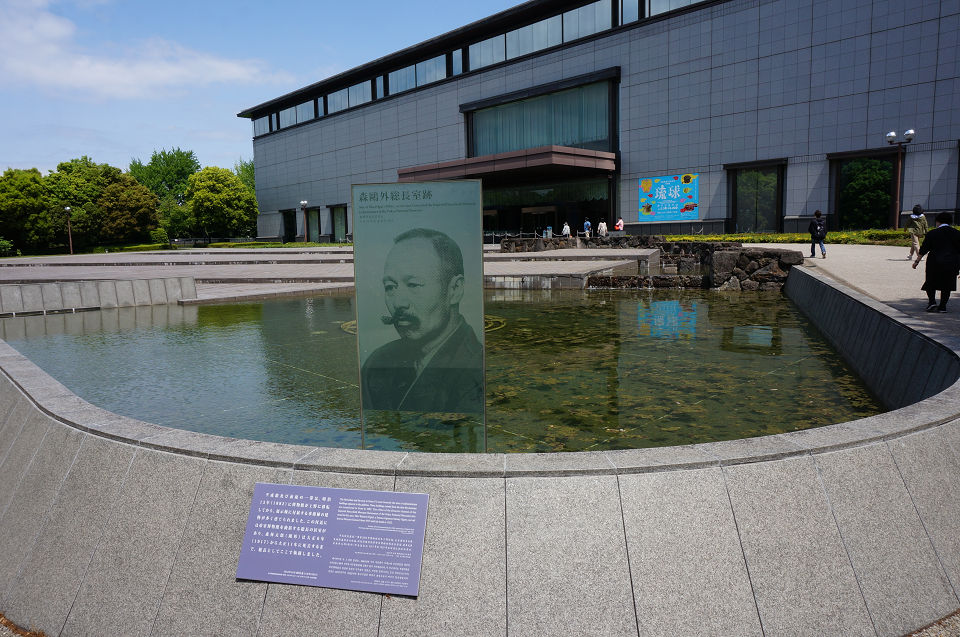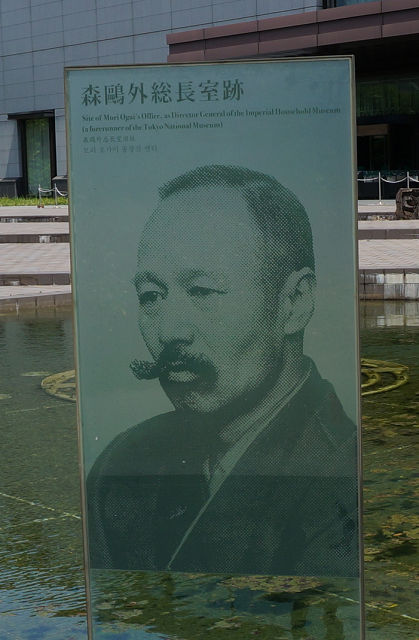駅を出ると本郷通りという少し大きな道路に出ます。本郷通りは途中までは国道17号線ですがこちらの交差点で左の細い道に分岐します。えっ!という感じですがこの細い道は由緒ある「中山道」なので一応国道なんですね。

起点となる日本橋から一つ目の一里塚があったそうで、旅のはじめのマイルストーンという感じですかね。

そして、その交差点の前にあるのは東京大学弥生キャンパスの農正門。

透かしの細工がいいですね。

ここは関係者でない一般人でも大学内に入って見学することができます。数人の個人見学ならば予約も不要です。東大に入学するのは難しいけどただ入るだけなら誰でもできるということですね。
こちらは農学部の校舎。1号館の校舎は竣工1930年でほぼ100年の歴史。生徒としては古臭くて不便そうですが部外者から見ると歴史ある校舎で学べるのは羨ましいですね。


こちらの農学部にある農学資料館には忠犬ハチ公の「臓器」が展示されているとか。ちょっと見学したいものではなかったので見ませんでしたが。
また、2019年ですが本郷三丁目駅寄りにある東京大学総合研究博物館で「家畜」の特別展示のポスターも貼ってありました。なかなか「濃い」ですね。

この農学部の片隅に朱舜水先生終焉の地の石碑。朱舜水は徳川光圀(水戸黄門)に教えを説いた中国(明)出身の儒学者。そう言えば水道橋にあある後楽園の「円月橋」の名付け親でしたね。

農学部のある弥生キャンパスから言問通りを挟んで隣の本郷キャンパスに行くために陸橋があります。こちらはドーバー海峡大橋と呼ばれているとか。

本郷キャンパス北側は工学部です。こちらも古いですね。

この錆びた巨大八角形の鉄板とか怪しげですね。

こちらの工6号館も上の部分が

ちょっと怪しげです。工学部らしくていいですね。

こちらは工学部1号館、国の有形文化財に登録されていますね。

この前の芝生広場にはこんな展示物もあったりします。

日本最先端の科学に多く携わっている大学ですからね。

この胸像はチャールズ・ウェスト、蒸気機関工学や機械製図など指導、日本の機械工学の発展に大きく寄与した人物だそうです。

こちらの銅像はジョサイア・コンドル、著名な建築家で鹿鳴館や海軍省、現存するものだと、旧岩崎久弥本邸や御茶ノ水のニコライ堂を設計してます。また、ここで建設工学の教鞭をとっていたそうです。

この横の法文学部1号館も有形文化財。



こちらの工学部列品館も有形文化財です。こんな場所で勉学できるって羨ましいですね。(若いときはそうは思わないかもしれないが)

(おまけ)こちらの側溝の蓋には「東大」と刻印してあります。特注なんでしょうね。

(つづく)